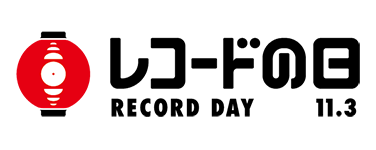カクバリズムから7インチ・シングルを出したポニーのヒサミツが語る大切な6枚のレコード
「ド・カントリーに行けるものなら行きたいけど行けない…ってジレンマはある。でも、日本人だし日本にいるし、今のメンバーと出会って一緒にやるようになった時に自然と落ち着いた場所がこのポニーのヒサミツなんです」
取材/文:岡村詩野
残念ながら見そびれてしまったのだが、先日、渋谷の『タワーレコード』でラヴィン・スプーンフルの紙ジャケットCD発売記念のインストア・イベントが行われた。そこで演奏していたのは、ポニーのヒサミツ、渡瀬賢吾(roppen)、谷口雄(ex森は生きている、1983)、サボテン楽団(という個人の音楽家)の4名。全員ボーダーのシャツを着て和やかにラヴィン・スプーンフルの曲(とNRBQの曲もやったそうだ)をプレイする様子は、さぞかしいい雰囲気だっただろうと想像できるが、ギスギスした空気をしょいこんだまま分散化している今の東京の一角で、自分の生まれた年よりはるか昔の時代の音楽風景に思いをはせることができる愛好家目線の強い若手音楽家たちが楽しげに呼吸をしながら演奏していることが何より素晴らしい、と実感する。
とりわけ、主に2010年代以降の東京で、あくまでポップスとしてのカントリーを軸足の一つとしてグッド・タイム・ミュージックを聴かせてきたポニーのヒサミツは、決して目立った存在ではないが大切な役割を担う重要人物だ。素直にいい曲を作るソングライターでありつつも、無邪気かつ確信犯的にカントリーや戦前フォークに踏み込んでいける良きリスナー。そして、愛すべき夢想家だと。ポニーのヒサミツと名乗っているものの、実際はヒサミツさんという名前のメンバーはいない、あくまで前田卓朗という現在30歳のシンガー・ソングライターを中心としたユニット。その前田=ポニーのヒサミツと名乗ることが多いようだ。シャムキャッツのメンバーも参加したファースト・アルバム『休日のレコード』(2013年)から3年、ようやく新しい作品として7インチ・シングル「羊を盗め」をカクバリズムよりリリースしたそんなポニーのヒサミツこと前田卓朗に、彼自身のキャリアにも触れつつ、フェイヴァリット・レコード6作品について語ってもらった。朴訥としつつもキリっとした言葉使いが印象的な話しぶりに触れながら、つくづく思った。こんなにレコード盤が似合う若手音楽家もそうそういない、と。
Harry Hosono&The World Shyness
『Flying Saucer 1947』(2007年)
「カントリーへの入り口になったアルバム」
「細野さんは僕にとって一番尊敬しているアーティストなので、どの時代の作品も好きなんですけど、この07年の作品で僕自身、古いカントリー音楽により興味を持つきっかけになったんです。細野さんは、この作品より前はしばらく歌ものから離れていて、ライヴではまた歌い始めていた頃なんですけど、久しぶりに歌に回帰したアルバムがカントリーだった、というのにまず面食らいまして。しかも、昔の持ち歌をカントリー・アレンジにする姿勢ですとか、1920年代~50年代の曲をカヴァーしていく姿勢ですとかが自分にはすごく新鮮だったんです。こんな風にカヴァーしていいんだ、「BODY SNATCHERS」も「SPORTS MEN」もこんなになっちゃうんだ、っていうのが衝撃で」
――ポニーのヒサミツの前に前田さんがやっていたstudent aは05年に活動を開始、ポニーのヒサミツは08年頃に活動を開始しているわけですが、ということは、07年に出たこのアルバムがポニーのヒサミツとしての前田さんの背中を大きく押したことにもなりますね。
「そうですね。それまではまだカントリーや戦前の音楽はほとんど聴いてなかったですから。このアルバムを聴いて、よりのめりこむようになったんだと思います。もちろん、それより前から古い音楽を聴いてはいましたし、家にプレイヤーもあって、両親のレコードもあったので、レコードで音楽を聴くこと自体にも親しんでいました。だから、ビートルズやカーペンターズとかはレコードで聴いていましたね。でも、その頃はもちろんそんな渋い趣味ばかりだったわけではなくて、普通にその時々で流行っている音楽も聴いてました」
――楽器を始めたのはいつですか?
「兄がギターを持っていたんですけど全然弾かせてくれなかったんで、中1の時に自分で買いました。最初はアコギで、中3の時にエレキです。ただ、僕は自分でギタリストだと思っている感覚ってあまりないんですよ。近くにいいギターを弾く仲間がいるので、僕が弾かなくてもいいやって、ここ数年どんどん強く思うようになっています(笑)。ギターという点でこの細野さんのアルバムを聴くと、ギターの音……徳武(弘文)さんも高田漣さんもそうですけど、すごく力の抜けた、いい演奏なんですよね。しかも構成が素晴らしい。自分でもこういう域に行きたいと思いつつ、今はまだまだなかなか…って感じです。ただ、レコーディングをちゃんとするようになってからは意識が変わってきましたね」
――ポニーのヒサミツとして『休日のレコード』をリリースしたのが2013年。つまり、その頃からだ、と?
「そうですね。ミュージシャンとしての自覚みたいなのを意識するようになったのは『休日のレコード』を録音する直前くらいのことなんです。しっかりバンド編成でやるようになってから、どういう歌い方が自分に合ってるのかな?って試行錯誤しているうちに、今のスタイルが歌いやすいことに気づいて。そこから徐々に「歌がいいね」とか「声がいいね」とかって言われるようになって」
――レコーディングの参考になるかどうかはわからないですけれど、細野さんのこのアルバムは2日で9曲を録音したそうです。そうした気のおけない仲間とのリラックスした雰囲気の中での録音スタイルが理想だったりするのでしょうか。
「この境地に行きたいなとは思ってますけど、まだまだトゥー・マッチな録音になっちゃう。行く行くはこの空気感を出せたらなと思ってます。一緒にやってくれているメンバー同士の共通理解がまず絶対に必要ですよね。あとは、まあ、僕自身がしっかり方向性……「こういうふうにしたい」ってことをバン!と示すとレコーディングがスムーズに行くんだろうなって。細野さんのこのアルバムからはそんなことも学んだりしますね」
――他アーティストの曲をとりあげる際の粋なセンスも細野さんのこの作品からは学べると思うのですが、ポニーのヒサミツも7インチ・シングル「羊を盗め」のカップリングでムーンライダーズの「スカーレットの誓い」をとりあげ、さらにはそのムーンライダーズのカヴァー・アルバム『BRIGHT YOUNG MOONLIT KNIGHTS -We Can’t Live Without a Rose- MOONRIDERS TRIBUTE ALBUM』にも参加しています(「犬にインタビュー」)。具体的に意識したポイントはありましたか?
「細野さん、ここ数年、ライヴでもカヴァーを多くやっているじゃないですか。それを聴いて「あ、こんな曲があるんだ」って知って、自分でそのオリジナルを探してきて聴いて…て感じがすごく楽しいんですよ。それと同じで、自分のカヴァーをきっかけに知ってもらえれば嬉しいなと思うんです。実際、僕自身、好きな曲をとりあげるのってすごく楽しいし、楽しんでレコーディングしたし。その感覚を聴いてくれる人と共有していきたいって思いますね」
――細野さんの曲をカヴァーしたことはあるんですか?
「ないんですよ。恐れ多くてなかなかできないです(笑)。お会いしたこともないです。でも、もしカヴァーするなら、細野さんのあまりカントリーっぽくない曲をカントリー・アレンジでやってみたい気がしますね。それこそこのアルバムでの「BODY SNATCHERS」みたいな感じです。「スカーレットの誓い」をカヴァーした時も、「BODY SNATCHERS」のこのアルバムでのヴァージョンを聴いて得た感覚でやってみたんです。そういう意味でも細野さんのこのアルバムは僕にとって何かと大きなきっかけになりましたね。カヴァーすること、カントリー・アレンジでやること……音楽に対する自由さという意味では本当に理想的なアルバムだと思います。細野さん自身、ライヴのトークで「カントリーいいですよ、2コードでラクですよ。若い人でもできます。」とか言ってたりしてすごい印象に残っています(笑)」
――でも、このアルバムは音がすごくいいですよね。ちゃんと今のシステムで録音されていて、今のオーディオで再生することを前提にしている。
「そうですね。古い機材にこだわって録音するようなこともやってみたいですけど、ちゃんとキレイに録れる環境でレコーディングしてあるのもいいなと思います。そこも共感できるというか。僕らも今回の「羊を盗め」をすごくいい環境で録音させてもらったんです。『休日のレコード』は、バンド録音は南池袋の『ミュージックオルグ』で機材を持ち込んでもらって録って、あとは自宅でも少し録って…って感じだったので、今回、ちゃんとしたスタジオでの環境で録音できてすごく新鮮でしたね」
Little Feat
『Sailing’ Shoes』(1972年)
「アメリカ南部の匂いと音への憧れ」
――カントリー好き、ルーツ音楽好きとしては、やはりアメリカの文化、歴史への興味は当然あると思うのですが、実際に訪ねたことはありますか?
「いや、家族旅行とかで小さい頃に行ったことはあるんですけど…。でも、特に南部の匂いがする音楽はやっぱり大好きで。いや、もちろん、高校の頃とかはUSインディーとかを聴いていたんですよ。ヨ・ラ・テンゴとか。でも、そこからルーツをどんどん遡るようになっていったんです。で、ザ・バンドもオールマン・ブラザーズ・バンドも好きになって……でも、特に「Willin」って曲が大好きで、それでその曲が入っているこのリトル・フィートのこのアルバムを今日は持ってきたんです。「Willin’」は音の重なり方とか音の鳴り方とか、すべて理想的な曲で。楽器構成として、アコギが入ってドラムが入ってピアノが入ってスティール・ギターが入って…って感じなんですけど、その入るタイミングとかフレーズとかが全て完璧だと思っているんです。まあ、全てが自分の好みで構成されている曲ってことなんですけど、正直、アルバム全体としてはザ・バンドとかの方が好きなものがあるんですけどね(笑)」
――リトル・フィートは西海岸で結成されたバンドですよね。ザ・バンドはリヴォン・ヘルム以外カナダ人。つまり、南部そのものってバンドじゃないのに、その匂いを伝えているのが面白い。
「そう、そこが面白いですよね。僕はちゃんと大人になってからまだアメリカには行ったことないんですけど、全く知らないで想像で曲を作ったりするのも面白いんじゃないかなって思うんですよね」
Little Feat「Willin’」
――しかも、このアルバムのプロデュースはテッド・テンプルマン。ハーパース・ビザールの元メンバーで、70年代後半にはヴァン・ヘイレンも手がけていくような、根っからのウェスト・コーストの人ですよね。
「そんな西海岸の人なのに南部に憧れてリトル・フィートをプロデュースして…って感じですよね。ローウェル・ジョージもザッパ・バンドにいたのに南部に憧れて…。この時代、割と世界中でそういう傾向にあったと思うんですけど、その感覚ってすごくよくわかるっていうか。今、日本人の僕は日本にいて、その土地のことはよくわかっていないから、アメリカ人としての感覚でそのまま出すことが出来ない、そのジレンマはすごくあるんです。でも、その憧れを日本人としてどう形にしていくのか。そういう意味で、細野さんの『Flying Saucer 1947』もそうですけど、目指す上でもすごく参考になるレコードですね。別に本当にその感覚を真似しなくても、想像力で豊かなことがどれくらいできるのかってことに挑戦したいというか。ここに行きたいけれど、なかなか行けない、でも、理解できるし、理解したいし、フェイクでも今の自分でやってみるということに励まされる作品なんですよね」《つづく》
- ポニーのヒサミツ
- カクバリズム
- 羊を盗め
- 私とレコード
- David Bowie
- Hoagy Carmichael & Orchestra
- The Beatles
- 細野晴臣
- Little Feat
- Rab Noakes