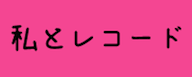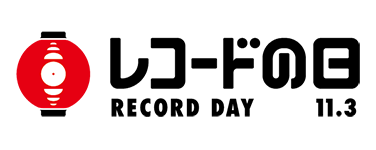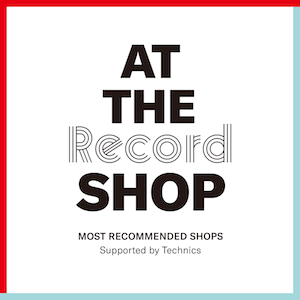蓮沼執太をつくったアナログ・レコード7選
『メロディーズ』(LP)を発売する蓮沼執太さん。先月公開したインタビュー(記事はコチラ)の取材時に、思い入れの深いレコード作品を7作品ご紹介していただきましたので、どうぞご覧ください。
Milford Graves 『 Percussion Ensemble』
これを手に取ったのは、たしか10代後半の頃だったかな。フリー・ジャズのドラマーやパーカッショニストもいろいろいますけど、そのなかでも僕にとってはこの人が一番。自分への影響云々ではなく、ただ単純にかっこいいっていう。彼とか、スティーヴ・リードみたいな、そこまでトライバルにならない感じのドラムが好きなんですよね。あと、これは本人がどう思うかわからないけど、メロディーズ・バンドの千住宗臣さんに近いものを感じます、個人的に。
Sun Ra 『 Space Is the Place』
これはもう、大名盤ですよね。それこそ10代の頃から好きだったんですけど、当時はこういうアルバムって、LPでしか買えなかったんじゃないかな。もちろんCDも出ていたんだろうけど、CDで聴くよりもレコードで聴く音楽なんですね。70年代に生まれた音楽だからこそ、自然とレコードのフォーマットで聴くことがしっくりきますね。
Terry Riley 『A Rainbow in Curved Air』
10代後半の頃は、フリー・ジャズとか、50~60年代のアーリー・エレクトロニクスと呼ばれるような初期電子音楽をたくさん聴きあさっていたんです。なかでもこれは特に名盤。デイヴィッド・バーマンというニューヨークの電子音楽の巨匠がプロデュースしています。僕のイメージは、テリー・ライリーは現代音楽文脈というよりもサイケロックやフージョンっぽいニューミュージックとして聴いていました。今は高値ですが、安くゲットした嬉しい記憶があります。
Vincent Gallo 『Recordings of Music for Film』
彼は超D.I.Y. なんですよね。ひとりで音楽作って、映画や写真を撮る。現代美術を知る前はカルチャーとして輝いて見えました。なにかとファッショナブルに扱われがちだけど、この人のつくるものからは美意識の高さが伝わってきていて、その追求する姿勢に好感を持てます。音楽としてはフリー・フォーク以降のもので、斬新さは薄いですけど、パーソナルな一面が垣間見れる事が良いですね。レーベルは〈ワープ〉からのリリースですね。
The Coctails 『Long Sound』
僕は90年代のシカゴのインディーズ音楽が大好きでした。92年にレコーディングされてる今作は、いわゆる音響派と呼ばれるムーブメントの前の作品ですね。なんかオシャレな音楽として見られることを嫌っていたように思います。それは彼らや周辺のミュージシャンがハードコアやパンクと言った、D.I.Y.精神を持っていたところや、電子音楽やインスト音楽などに傾倒していった姿勢が好きだったんでしょうね。そういうところには大きく影響を受けていると思います。
Bonnie ‘Prince’ Billy 『Master and Everyone』
意識してなかったんだけど、今回は顔のジャケットばかり選んでますね(笑)。それはともかく、ボニーに関しては、もう単純にファン。オンリーワンな個性であり、絶対に自分ではなれない存在であって、やっぱりカリスマ性の高さがかっこいい。Palace Musicのときからずっと好きですけど、なかでもやっぱりこのアルバムはよく聴いてしまいます。
細野晴臣 『フィルハーモニー』
この帯文、すごいですよね。「一生懸命作りました。」って。でも、その通りなんだと思います。この時代って、まだシンセサイザーや電子楽器の使い方が決まってなくて自由さを感じます。その手探りな感じが素晴らしいです。僕らのような音楽家は当然新しいことを目指して頑張っていくのですが、その新さというのは先人が築いてきた文脈があることを忘れてはいけないし、だからこそ新さに挑戦できるのだと思います。
取材/文:渡辺裕也
撮影:豊島望
- 蓮沼執太
- メロディーズ
- Milford Graves
- Sun Ra
- Terry Riley
- Vincent Gallo
- The Coctails
- Bonnie ‘Prince’ Billy
- 細野晴臣
- 私とレコード
- 東洋化成ONLINE SHOP